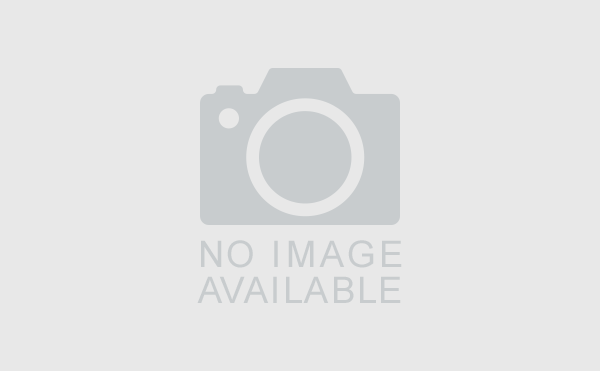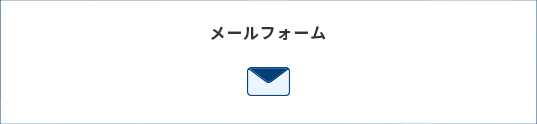殺傷能力の有無 伊藤
江戸時代に大八車で死亡事故を起こすと死罪になる、というのは悪質な事故が多くて厳罰化する必要に迫られた結果ということ。悪質という印象になる原因としては、車両の重量が一定以上でスピードが加われば十分な殺傷能力があるということ、止まるための機構がおそらく無かったこと、牛や馬に引かせている場合それが暴れたときにコントロールを失ってしまうこと。そういうものに轢かれて殺されてしまうのは理不尽だ。十分な殺傷能力を有する物が、何かの弾みでコントロールを失ってしまったり不具合や不注意で近くの人間に危害を加える可能性がある場合、その器具は安全柵の中だけで使用するべきで、野に放つべきではない。現代の産業用機械の取り扱いとして考えた場合、これはごく当たり前だ。大八車に轢かれるのと、現代の車に轢かれるのと、どっちの話だったか分からなくなってきた。協働ロボットは誰かが間合いに侵入したら停止する。このイメージを4輪自動車に割り当てた場合、車でうっかり駅前に侵入するとその車は終電時間まで動けなくなる、ぐらいが順当なところだと思う。殺傷能力で考えると、(A)車に乗って駅前に行く、と、(B)日本刀を持って駅前に行く、の間にはびっくりするぐらいの共通点がある。A、Bの行動をする主に、①殺意がある場合、②殺意は無いが過失が発生した場合、③殺意がなく過失も発生しない場合、どのケースでも死傷者の出る出ないの結果は同じとなりそう。もちろん車の道具としてのカテゴリーは「乗り物」で日本刀は「武器」だから同列に語るべきでない、と言いたいところだけど、身内や大切な人の命が交通事故で奪われた時にそんなセリフが言えるか、江戸時代の交通事故が厳罰化した背景やイメージからそんなことを思う。