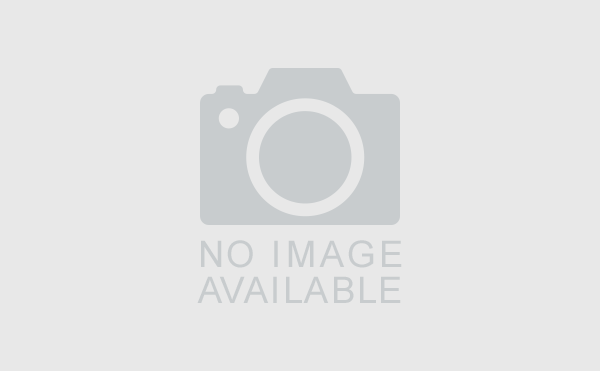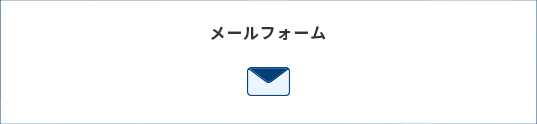物流メインではない 伊藤
ウィキペディアでも「日本の古代道路」のページがあって、7世紀あたりの道路の情報がある。当時の広い幅の道は、中央(たぶん奈良のこと?)と地方を結ぶ情報伝達のための道・駅路と呼ばれていて、16キロ間隔に駅家(うまや)があり、そこには駅馬が何頭か待機していて、これをレリーで繋いで情報を伝達していたみたい。これが駅伝制。道は広いだけでなく、なるべく直線になるように出来てたそうで、現代の高速道路やインターチェンジと重なる部分も多いんだそうな。主な目的は情報の伝達であって、物流が目的であればあの街とこの街を繋いで・・となりそうな部分を無視して、あくまで情報伝達の速さを重視しているそう。この頃の物流の主役は水路だったそうで、陸路で大量の物流という発想はそもそも無かったのかも。車輪や車両の発達する前では確かにそうなのかもと思う。当時の車輪や車両がどういうものだったのか調べると面白そう。