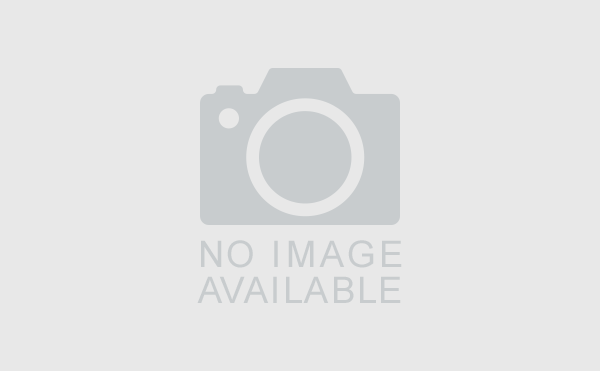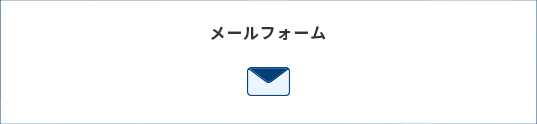DMG森精機 レポート1 伊藤
レポート
9月14日はDMG森精機のセミナーへ行きました。一部はDMG森精機によるインダストリー4.0への提案、二部はトヨタのパワートレーン企画部の方による、車作りと工作機業界のこれからの関係について、三部はDMG森精機の実機デモ、の三部構成でした。
一部 インダストリー4.0
ちょくちょく目にする単語ですが、具体的には、自国の製造業高度化に向けてドイツ政府が立てたコンセプト、その名前がインダストリー4.0だそうです。パッとイメージが浮かぶのは、高付加価値、高能率を実現するために、ハイテク情報技術などを駆使したりIoTの話の雰囲気が強そうな気がしますが、もっと多岐にわたる事であるようです。
自動化の部分から話は入り、MCにワークをセットを自動化する装置として、古くからパレットチェンジャー(ワークがセットされたパレットがずらっと並べてあって、搬送機がMCの中へそれをとっかえひっかえしてくれる)がありますが、もっと省スペースでフレキシブルな物として多関節のロボットアームを使ったシステムがあり、カメラやセンサーを併用することで、バラバラな方向に転がっているワークを適切に拾いセットすることもできるようです。こういったものも今や特注のシステムではなく、パッケージ化されてMCの横につけるオプションのような形で用意されているようです。加工前にツールチェンジャーの中に必要なツールを揃えておくのは当たり前ですが、ワークも次のワーク、その次のワーク、さらにその次のワークをさっと取り替えられるように用意しておく事が出来れば、確かにとても効率的です。しかし今のところ同一形状を量産するためのシステムとしての性格が強そうです。
次にセンサー類です。MCにはいろんなセンサーが入っています。工具長測定のタッチセンサーや、ワーク座標の基準をとるプローブは昔は無かった装置で、他の道具と人間の作業の組み合わせで、その代わりをしていました。ワンタッチで出来るようになって、とても便利になりました。スピンドルの負荷や各軸の駆動負荷も数値で常に表示されています。最近のMCではセンサーの数がさらに増え、ビビリの検出のセンサーなんかも入っているそうです。ビビリを検出すると、回転と送り速度を変更する提案をMCが作業者へ出してくれるようです。変更された加工条件は保存され、次の加工ではその加工条件が適用される、という蓄積も出来るようです。その他たくさんのセンサーが各部の状態を常に監視し記録し続けるようです。そろそろメンテナンスが必要と判断すると、作業者にメンテナンスの勧めるようです。センサーからの情報をうけて、回転を調整したりメンテナンスを勧めたりする判断をするのがMCに組み込まれたセロスというOSで、CAMオペレーターから加工の注意事項等をMC作業者に伝達したり、MC作業者からCAMオペレーターへ加工条件変更を提案する等の、前工程との円滑な情報交換もサポートしてくれます。トラブルがあった際もMCの状態を直接サポートセンターへ送ることができ、リモートサポートまでできるようです。制御装置の取っ付きやすさが1歩進んだ感じで、ちょうどパソコンの歴史でいうと、NECの88とか98の真っ暗の画面に文字を入力するだけの時代から、ウインドウズの時代に移ったような雰囲気がしました。もう少し進歩すると、MCの画面に加工指示書と自由に動かせる3Dビューが表示されて、それを見ながらワークをセットできるようになるのではないかと思います。
ソフト面の進歩が、目を見張るものがある気がします。より柔軟に、シンプルな操作性に、フレキシブルに、かゆいところに手が届く、ようになっています。
センサーが増えたのは、状態の把握に必要な情報がそれだけあるということです。ソフトの進歩は、センサー情報を適切に意味付けしてさまざまに活用する仕組みを発展させると、こんなにい良いことがいっぱいあるんだと教えてくれます。
情報と仕組みに注目、という事になります。これはMCや設備に限ったことでは無いと思います。より良い仕組みを作り、それが機能するために必要な情報に注目する。仕組みは常にアップデートされていきます。そこに柔軟に対応するのは、機械よりも人間の方が得意だと思います。
次回は、第2部の話をレポートしたいと思います。